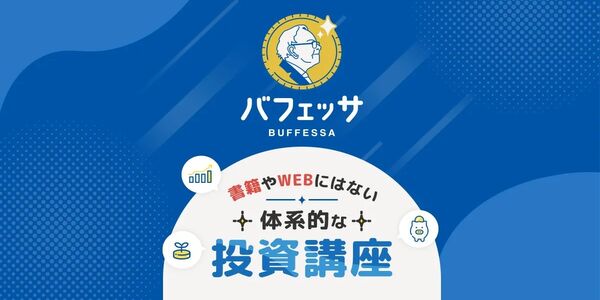ダウ理論の重要性とその影響
ダウ理論は、株式市場や外国為替(FX)市場などの金融市場において非常に重要な分析手法の一つです。
この理論は、市場のトレンドや価格動きを理解するための基本的なフレームワークを提供し、多くのトレーダーが参考にしています。
ダウ理論の起源とその意義
ダウ理論は、アメリカのジャーナリストであり、ウォールストリートジャーナルの創設者でもあるチャールズ・ダウによって考案されました。
この理論は、1890年代に誕生し、株式市場の動きを予測するための基礎となっています。
ダウは、市場価格にはすべての情報が反映されるという考えから出発しました。この「市場は全知全能」の前提に基づき、ダウ理論は発展しています。
ダウ理諫の基本要点:トレンドと確認
ダウ理論は基本的に3つの主要なトレンドに焦点を当てています:主要トレンド(長期)、二次トレンド(中期)、短期トレンドです。
これらのトレンドは互いに影響し合い、市場の全体像を形成しています。
さらに、ダウは価格動きを確認するためには、複数の市場指数を用いることが重要だと説いています。
例えば、ダウ・ジョーンズ工業平均株価とダウ・ジョーンズ輸送株平均が共に新高を更新している場合、強い上昇トレンドが確認されるとされています。
ダウ理論の影響とその活用法
ダウ理論は多くのテクニカル分析の基礎ともなっており、RSI、MACD、移動平均線など、多くのテクニカル指標がダウ理論に影響を受けています。
実際のトレードにおいては、ダウ理論を用いて市場のトレンドを判断し、エントリーやエグジットのタイミングを決定することが多くあります。
しかし、ダウ理論には批評も多く、必ずしも全ての市場環境に適用できるわけではありません。そのため、他の分析手法と組み合わせることが一般的です。
▼テクニカル分析についてもっと詳しく知りたい方はこちら
デイトレードにおけるテクニカル分析のコツや注意点、取引手法を紹介!
トレードのテクニカル分析に意味はないのか?基礎知識や分析の方法、コツを紹介
まとめ
ダウ理論は、トレードの世界で広く受け入れられている重要な理論ですが、それだけで市場を予測するのは危険です。
他のテクニカルやファンダメンタル分析と組み合わせることで、より確実なトレード戦略を構築することが可能です。
ダウ理論の起源:チャールズ・ダウとは?
ダウ理論は、株式市場やFX市場でよく使われる分析手法の一つですが、この理論の背後にはどのような歴史や人物がいるのでしょうか。
今回は、ダウ理論の創始者であるチャールズ・ダウに焦点を当て、彼がどのようにしてこの画期的な理論を生み出したのかについて詳しく解説します。
チャールズ・ダウの背景と彼が目指したもの
チャールズ・ダウは、1851年にアメリカで生まれました。
彼はジャーナリストとしてのキャリアをスタートし、後にウォールストリートジャーナルの創設者となります。
ダウは、一般の投資家が市場の動きを理解する手助けをするために、自らの観察と分析を基にダウ理論を考案しました。
彼の目的は、複雑な金融市場をよりアクセスしやすく、理解しやすいものにすることでした。
ダウ理論の誕生:ダウの観察と洞察
ダウ理論が誕生したのは、1890年代のことです。
当時、チャールズ・ダウはウォールストリートジャーナルで、自らが考案したダウ・ジョーンズ平均株価という指数を用いて、市場の分析を行っていました。
彼がこの理論を形成した背後には、市場は効率的であるという前提があります。
すなわち、市場価格はすべての利用可能な情報を反映していると考えました。
ダウは、価格の動きやトレンドに一定のパターンが存在すると確信し、それを体系化したのがダウ理論です。
チャールズ・ダウの遺産とダウ理論の影響
チャールズ・ダウは1902年に亡くなりましたが、彼が生み出したダウ理論は今もなお、多くのトレーダーに影響を与えています。
この理論は、テクニカル分析の基礎ともされ、後の多くの分析手法の発展に寄与しています。
特に、ダウの「市場には三つのトレンドが存在する」という考えは、多くのトレーダーがトレンド分析に利用しており、現代の多くのテクニカル指標にも影響を与えています。
まとめ
ダウ理論の創始者であるチャールズ・ダウは、独自の観察と分析に基づき、一般の投資家が市場を理解しやすいようにとこの理論を考案しました。
彼の影響は現代にも続いており、多くのトレーダーがダウ理論を基にして投資判断を行っています。
この理論がどのようにして生まれ、どのように進化してきたのかを知ることは、現代の投資家にとっても非常に価値のある知識と言えるでしょう。
・100円から取引可能
・業界最狭水準スプレッド 0.2銭
・初心者も始めやすい自動売買
ダウ理論の基本要素:価格とトレンド
投資やトレードにおいて、市場の動きを正確に予測することは非常に重要です。
その中でよく用いられる理論がダウ理論ですが、この理論は一体どのように価格やトレンドと関係しているのでしょうか。
今回は、ダウ理論の基本要素として、「価格」と「トレンド」について深掘りしていきます。
価格は全ての情報を反映する
ダウ理論の根底には、「価格は全ての情報を反映している」という考えがあります。
この考え方は、市場に関連するあらゆる要因(企業の業績、政治的状況、自然災害など)が最終的には価格に反映されるというものです。
ですから、価格の動きを正確に解析することで、その後の市場の動きもある程度予測することが可能とされています。
三つのトレンド:主要トレンド、中期トレンド、短期トレンド
ダウ理論では、市場には「主要トレンド」「中期トレンド」「短期トレンド」という三つのトレンドが存在するとされています。
主要トレンドは、長期間にわたって続く市場の大きな動きを指します。
一方、中期トレンドと短期トレンドは、それぞれ数週間から数ヶ月、数日から数週間の期間で発生する市場の動きを指すものです。
これらのトレンドをうまく捉えることで、より効率的なトレードが可能となります。
トレンド確認の手法:高値と安値
トレンドを確認する基本的な手法として、高値と安値の動きを追う方法があります。
新しい高値が出た場合、それは上昇トレンドの一部である可能性が高いです。
逆に新しい安値が出た場合、それは下降トレンドの一部と考えられます。
この高値と安値の動きを注意深く観察することで、どのトレンドに市場があるのかを判断する材料とすることができます。
まとめ
ダウ理論は、価格とトレンドに基づいて市場の動きを分析する理論です。
価格が全ての情報を反映しているという前提に基づき、主要トレンド、中期トレンド、短期トレンドの三つのトレンドを用いて市場分析を行います。
そして、高値と安値の動きを通じて、そのトレンドを確認します。
この基本的な要素を理解することで、より効果的な投資やトレードが可能となります。
ダウ理論の6つの法則
投資やトレードの世界でよく聞くダウ理論。
しかし、この理論が何を意味し、どのようにトレードに活かせるのかは一筋縄ではいかないテーマです。
特に重要なのが、この理論が提唱する「6つの法則」です。
この記事では、ダウ理論の6つの法則について詳しく解説し、それぞれの法則がどのようにトレードに活かせるのかを見ていきましょう。
1. 市場には全ての情報が反映される
この法則は、株価や為替レートなど、市場の価格には全ての情報が反映されているという考え方です。
政治的な出来事や経済指標、企業の業績など、さまざまな要因が市場に影響を与えますが、これらは全て最終的に価格に反映されるとされています。
この法則を理解していると、価格の動きに注目することで市場全体の状況を把握することが可能です。
▼FX市場についてもっと詳しく知りたい方はこちら
専業トレーダーに必要な資質とスキル!FX市場で生計を立てるためのヒント
ニューヨーク・ロンドン・東京: FX時間帯別の市場動向と特徴
2. 市場はトレンドを形成する
市場は常に何らかのトレンド(上昇、下降、横ばい)を形成しているというのがこの法則です。
ダウ理論では、トレンドは「主要(長期)」、「中期」、「短期」の3つに分けられます。
これらのトレンドを正確に読み取ることで、適切なエントリーとエグジットのタイミングを計ることができます。
3. 主要なトレンドは3つのフェーズに分けられる
この法則では、主要なトレンドは「蓄積フェーズ」、「参加フェーズ」、「過熱フェーズ」の3つのフェーズに分けられます。
蓄積フェーズでは市場の専門家が静かにポジションを取り始め、参加フェーズでは一般の投資家が市場に参加し始め、過熱フェーズでは市場が楽観的になりすぎて価格が急騰します。
これを理解することで、市場の状況に応じた戦略を考えることができます。
4. 平均は必ず確認する
この法則によれば、一つの価格指標だけでなく、複数の平均価格も確認する必要があります。
例えば、ダウ・ジョーンズ工業平均株価とダウ・ジョーンズ運輸株価指数など、異なるセクターの平均価格を比較することで、市場の健全性を評価できます。
5. ボリュームはトレンドを確認する
取引量(ボリューム)もトレンドの確認に非常に重要です。
ボリュームが伴っている場合、そのトレンドはより確かであると考えられます。
逆に、ボリュームが低いと、トレンドが終息する可能性が高いです。
6. トレンドは明確な信号が出るまで続く
最後の法則は、トレンドは明確な反転の信号が出るまで続くというものです。
つまり、単に価格が下がったからといって、すぐにトレンドが終了するわけではありません。
反転の明確な信号が出るまで、トレンドは続くと考えるべきです。
まとめ
ダウ理論の6つの法則を理解することは、市場の動きを読み取る上で非常に役立ちます。
各法則が具体的にどのような意味を持ち、どのようにトレードに活かせるのかを知ることで、より高度な投資戦略を練ることが可能です。
ぜひ、これらの法則をマスターして、効果的なトレーディングを行ってください。
トレンドの三相:積み上げ、参加、分配
投資やトレードを行う際に、市場の動きを正確に把握することが成功の鍵となります。
そのために役立つコンセプトが、ダウ理論における「トレンドの三相」です。
この記事では、トレンドがどのように「積み上げ」、「参加」、「分配」の三相を経るのか、それぞれの相で何が起こっているのかを詳しく解説します。
積み上げ相:市場の専門家がポジションを形成
積み上げ相は、トレンドの最初の段階です。
この段階では、市場の専門家や大手投資家が新しいトレンドを見抜き、積極的にポジションを形成します。
一般的な投資家がまだ参加していないこの段階では、価格変動は比較的小さいものが多いです。
しかし、この相が終わると、次の「参加相」に移行し、より多くの投資家が市場に参加することになります。
参加相:一般の投資家が市場に参加
参加相は、トレンドが明確になり、一般の投資家も市場に参加する段階です。
この相では、メディアやニュースで取り上げられることが多く、多くの一般投資家が市場に参加します。
これにより、価格は急速に動き、トレンドがさらに強まることが多いです。
ただし、この段階では既に専門家や大手投資家がポジションを持っているため、遅れて参加するとリスクも高まります。
分配相:トレンドの終焉と利益確定
分配相は、トレンドがピークに達した後、逆の動きが始まる前の段階です。
この段階では、早くからポジションを持っていた専門家や大手投資家が利益を確定するために売り始めます。
一般的な投資家はこの段階でようやく気づくことが多く、結果として損失を被る可能性が高いです。
この相を見極めることができれば、適切なタイミングでポジションを閉じることが可能となります。
まとめ:三相理解の重要性と活用方法
トレンドの三相を理解することは、効果的なトレード戦略を練る上で非常に重要です。
各相が何を意味し、どのようにトレードに活かせるのかをしっかりと把握しておくことで、より賢明な投資判断が可能となります。
特に、分配相での早期利益確定や、積み上げ相での早めの参加が成功のカギとなる場合が多いです。
この知識を活かして、賢い投資を行いましょう。
ダウ理論とテクニカル指標
投資やトレードの世界において、市場の動きを読む手法は多岐にわたります。
その中でも特に注目されるのが、ダウ理論とテクニカル指標です。
これらは一見別々のアプローチに見えますが、実は密接な関連性があります。
この記事では、ダウ理論とテクニカル指標がどのように連携し、投資戦略にどう活かせるのかを詳しく解説します。
▼テクニカル指標についてもっと詳しく知りたい方はこちら
FXテクニカル指標の基本: トレードの成功への第一歩
トレーダーによく使われているテクニカル指標を徹底解説!読み方・使い方を徹底網羅
ダウ理論の基本とテクニカル指標の関係
ダウ理論は、市場のトレンドを理解するための基本的な枠組みです。
この理論は、市場の主要な動き(主トレンド)、中期的な動き(中間トレンド)、短期的な動き(短期トレンド)を把握するために用います。
一方、テクニカル指標は、これらのトレンドを数値やグラフで可視化するツールです。
例えば、移動平均線は中期的なトレンドを、RSI(相対力指数)は短期的な過買や過売状態を示します。
このように、ダウ理論の観点から得られた洞察をテクニカル指標で補完することができます。
▼RSIについてもっと詳しく知りたい方はこちら
RSIとは?見方や取引での使い方、分析方法などを紹介!
完全攻略!FX RSIの正確な期間設定と売買タイミング
どのテクニカル指標がダウ理論に適しているか
ダウ理論に基づく分析には、特定のテクニカル指標が特に有用です。
例えば、MACD(移動平均収束拡散)は、主トレンドに沿ったエントリーとエグジットのタイミングを明示的に示す場合が多いです。
また、ボリンジャーバンドは価格の変動幅とトレンドの強さを示し、ダウ理論の「市場にはすべてが織り込まれている」という考え方とも合致します。
このように、テクニカル指標を選ぶ際には、ダウ理論のどの側面を補完したいかを考慮すると良いでしょう。
ダウ理論とテクニカル指標の限界
もちろん、ダウ理論とテクニカル指標にもそれぞれ限界があります。
ダウ理論はあくまで市場の心理を読む一つの枠組みであり、絶対的なものではありません。
また、テクニカル指標は過去のデータに基づいていますので、未来を100%予測するものではないことを理解する必要があります。
したがって、これらを組み合わせて使用する際には、他の分析手法やファンダメンタルズも考慮することが重要です。
まとめ:ダウ理論とテクニカル指標の効果的な使い方
ダウ理論とテクニカル指標は、投資戦略を構築する際の強力なツールですが、それぞれの手法には独自の強みと弱点があります。
この二つを効果的に組み合わせることで、より堅実で洗練されたトレード戦略を練ることが可能です。
特に、ダウ理論の基本的な考えを理解した上で、それを補完する形でテクニカル指標を活用することが、成功への一歩と言えるでしょう。
ダウ理論を活用した実践的なトレード戦略
投資やトレードにおいて成功するためには、多くの場合、理論と実践の組み合わせが求められます。
ダウ理論は、株やFXの市場分析に広く用いられる理論の一つですが、この理論を実際のトレード戦略にどう組み込むかが重要です。
本記事では、ダウ理論を活用した実践的なトレード戦略について解説します。
▼トレード戦略についてもっと詳しく知りたい方はこちら
FXの水平線とトレンドライン活用術:正確な線の引き方と効果的なトレード戦略
トレード戦略のパターン:あなたの投資スタイルに最適なものは?
ダウ理論に基づいたエントリーとエグジット
ダウ理論に基づいて市場を分析すると、大きなトレンドを見つけることができます。
主トレンドが上昇している場合、買いポジション(ロング)を取る方が有利です。
逆に、主トレンドが下降している場合は売りポジション(ショート)を取る方が良いでしょう。
さらに、中期トレンドや短期トレンドを用いて、エントリーとエグジットのタイミングを最適化することが可能です。
具体的には、短期トレンドが主トレンドと同じ方向に動いているタイミングでエントリーし、逆に動き始めたところでエグジットするという戦略が考えられます。
ダウ理論と他のテクニカル指標の組み合わせ
ダウ理論自体が非常に強力な分析手法である一方、他のテクニカル指標と組み合わせることで、さらに効果的なトレード戦略を練ることができます。
例えば、MACDやRSIなどのオシレーター型指標は、ダウ理論によって見つけたトレンドの強さや、過買・過売状態を確認するのに役立ちます。
また、移動平均線を用いることで、主トレンドがまだ健在かどうかの確認も容易です。
これらの指標を用いて、ダウ理論に基づいたエントリーやエグジットのタイミングを補完することができます。
ダウ理論を活用したトレード戦略のリスク管理
成功するトレードには、効果的なリスク管理が不可欠です。
ダウ理論に基づいたトレード戦略でも、例外ではありません。
一般的に、トレンドが逆行した場合や、市場のボラティリティが急に高まった場合には、損切りを早めに行うことが重要です。
また、ポジションサイズを適切に設定し、利益を最大化しながらリスクを抑制することも大切です。
さらには、複数の時間軸でトレンドを分析することで、より確実なエントリーとエグジットを行うことが可能です。
まとめ
ダウ理論を活用した実践的なトレード戦略は、理論的な知識と具体的なテクニックの組み合わせによって高度になります。
この記事で解説したように、エントリーとエグジットのタイミング、他のテクニカル指標との組み合わせ、そしてリスク管理の方法を理解し、それを実践に移すことが、成功への鍵となります。
ダウ理論の限界と欠点
ダウ理論は株やFXのトレードにおいて、多くの投資家が参考にする価格分析のフレームワークです。
しかし、どんな理論にも限界と欠点は存在します。
本記事では、ダウ理論の不完全性やリスクについて、詳しく解説します。
予測の限界:反転ポイントの特定が難しい
ダウ理論は市場のトレンドを把握することに優れていますが、トレンドが逆転する瞬間を正確に予測するのは難しいとされています。
特に、短期的な価格変動においては、ダウ理論が提供する情報は限られます。
これは、短期的な価格変動は多くの場合、感情や短期的なニュースなど、非理論的な要素によっても影響されるからです。
よって、ダウ理論だけに頼ると、短期的なトレードでリスクが高まる可能性があります。
時代背景との不一致:テクノロジーの進化と市場環境の変化
ダウ理論は19世紀後半に考案されたもので、当時と現代の市場環境は大きく異なります。
例えば、現代の市場は高度に電子化され、アルゴリズムトレードなど、新たな取引スタイルが登場しています。
これによって、市場の動きが急激に変わることがあり、ダウ理論だけでは対応しきれない場合があります。
また、社会的な要素や政治的な出来事による影響も、ダウ理論では十分に説明できない場合が多いです。
他の指標との組み合わせが必要:ダウ理論だけでは不十分
ダウ理論はあくまで一つのフレームワークであり、多くの場合、他のテクニカル指標やファンダメンタル分析と組み合わせる必要があります。
単独でダウ理論を用いると、トレンドの把握はできるかもしれませんが、その他の多くの要素(ボリューム、モメンタム、買い圧力など)は無視されてしまいます。
そのため、ダウ理論だけを頼りにトレードを行うと、多角的な分析ができずにリスクが高まる可能性があります。
まとめ
ダウ理論は確かに強力な分析手法の一つですが、それだけでは市場の全てを把握するのは難しいです。
予測の限界、時代背景との不一致、他の指標との組み合わせが必要など、ダウ理論の限界と欠点を理解することで、よりバランスの取れたトレード戦略を練ることができます。
これらの点を考慮に入れ、ダウ理論を上手く活用しましょう。
投資を本気で頑張りたい人には投資講座「バフェッサ」がおすすめ
ここまで記事を読んだ方の中には、
「今後も物価が上がり、生活費も上がり続ける・・・」
「安定企業は無い・・・」
「簡単に給料も上がらない・・・」
といった方も多いと思います。
そんなあなたに、数字や経済が苦手な人でもたった2時間の動画を見るだけで月2万円で数千万円を目指せる、「バフェット流 新NISA講座 バフェッサ」のご紹介です。
投資講座「バフェッサ」は、
・累計受講者数:40万人以上
・満足度93%
・期間限定で無料で提供中
のいま注目の投資講座です。
「効率よく投資を勉強したい」
「基礎からちゃんと投資について学びたい」
といった方にはおすすめの講座となっています。ぜひお気軽に申し込みしてみてください。
ダウ理論と他の投資理論との比較
投資の世界には多くの理論と戦略が存在しますが、その中でもダウ理論は非常にポピュラーです。
しかし、ダウ理論が全ての状況で有効なわけではありません。
今回は、ダウ理論と他の主要な投資理論との比較を通じて、各理論の特性や適用シナリオを理解することを目的とします。
ダウ理論とエリオット波動理論:トレンドの認識
ダウ理論は市場のトレンドを読むための基本的なフレームワークですが、エリオット波動理論はより高度なトレンド分析を提供します。
ダウ理論は主に大きなトレンド(主要トレンド、中期トレンド、短期トレンド)に焦点を当てています。
一方で、エリオット波動理論は市場が形成するさまざまな波(5つの波で構成される主要な動きと、それを修正する3つの波)を分析します。
エリオット波動理論は、ダウ理論よりも複雑なパターンを解析するためのツールとされています。
ダウ理論とファンダメンタル分析:価格と価値の違い
ダウ理論はテクニカル分析の一部であり、主に価格とボリュームを用いて市場を分析します。
一方、ファンダメンタル分析は、企業の財務状況や市場環境を詳細に調査して、株の「真の価値」を求めます。
ダウ理論が「価格は全てを反映する」とするのに対し、ファンダメンタル分析は「価格と価値は必ずしも一致しない」と考えます。
この差異は、短期トレードと長期投資の戦略に大きな影響を与える可能性があります。
ダウ理論と量価分析:ボリュームの重要性
ダウ理論は主に価格に関心を持ちますが、量価分析は価格とボリュームの関係性に更なる注目を向けます。
量価分析では、ボリュームが増加すると、その方向のトレンドが強まると考えられます。
例えば、価格が上昇するときにボリュームも増加していれば、その上昇トレンドは継続する可能性が高いとされます。
ダウ理論もボリュームを考慮しますが、量価分析ではそれに更に深く焦点を当てるため、補完的に使用すると有効です。
まとめ
ダウ理論は投資とトレードにおいて広く使用される基本的な理論ですが、他にも多くの分析手法が存在します。
エリオット波動理論での高度なトレンド分析、ファンダメンタル分析での価値評価、量価分析でのボリュームの考慮など、他の理論と組み合わせることで、ダウ理論の限界を補完することが可能です。
それぞれの理論と戦略には特有の利点と限界があり、それを理解して柔軟に適用することが成功への鍵です。
まとめ:ダウ理論を理解し、効果的に活用するために
ダウ理論は、株やFXなどの金融市場でよく使用される分析手法です。
多くのトレーダーがこの理論を活用していますが、正確に理解し、効果的に活用するためにはどうすればよいのでしょうか。
今回は、ダウ理論の基本的な6つの法則、それをトレード戦略にどう活かすか、そしてその欠点について解説します。
6つの基本的な法則を理解する
ダウ理論は、6つの基本的な法則に基づいています。
- 市場には3つのトレンドが存在する。
- 市場は全ての情報を反映する。
- 株価は需要と供給によって決まる。
- 平均は必ず一致する。
- トレンドは確認されるまで続く。
- ボリュームはトレンドを確認する。
これらの法則を理解することで、市場の動きに柔軟に対応することが可能になります。
市場のトレンドを正確にキャッチし、そのトレンドが継続するか逆行する可能性があるかを評価することができます。
トレード戦略への活かし方
ダウ理論を効果的に活用するためには、トレード戦略に組み込む必要があります。
- トレンド確認:主要なトレンドが確認された場合、その方向にポジションを取ることが基本です。
- リスク管理:ダウ理論に基づいて、ストップロスの位置を決定します。
- エントリーとエグジット:中期トレンドや短期トレンドを利用して、エントリーとエグジットのタイミングを見極めます。
具体的なトレード戦略とダウ理論を組み合わせることで、より確実な投資判断が可能になります。
欠点とその対処法
ダウ理論にはいくつかの欠点も存在します。
- 過去のデータに依存する:ダウ理論は歴史的な価格データに基づいているため、未来を予測するものではありません。
- 主観性:トレンドの確認や解釈には主観が介入する可能性があります。
- ノイズ:短期的な価格変動(ノイズ)を過度に反映してしまう可能性があります。
これらの欠点を補うためには、他のテクニカル指標やファンダメンタル分析を併用することが有効です。
まとめ:ダウ理論を理解し、効果的に活用するために
ダウ理論は、多くのトレーダーにとって基本的な分析手法ですが、その効果的な活用方法や限界も理解する必要があります。
6つの基本法則を把握し、自分のトレード戦略にどう取り込むかを考えましょう。
また、ダウ理論の欠点を理解して、他の分析手法と組み合わせることで、より堅牢な投資戦略を構築することが可能です。
ーーーーー
トレードの人気記事
・おすすめのネット証券10社を紹介|初心者が気にすべきポイントは?
・スイングトレードはなぜ難しい?ほかの手法との違いや取引の注意点、初心者がハマる罠について解説
・ポジショントレードとは?他の取引手法との違いやメリット・デメリット、取引のコツを紹介
・初心者のためのデイトレードを徹底解説!他の手法との違いや取引のコツ、注意点やリスクを解説!
・短期トレードを徹底解説!スキャルピングやデイトレード、初心者が取引するためのコツや注意点を解説!
・“コツコツドカン”の原理、治す方法や対策方法を解説
・1時間足、5分足、15分足… どれがベスト?FXデイトレードの時間足徹底解説
・スイングトレードとは?メリット・デメリットやスキャルピングやデイトレードの違いなどを解説!